ニューオーリンズ・ミュージックのCD
HOME ・ INDEX ・ BLUES ・ SOUL/FUNK ・ ROCK
LIFE IS A CARNIVAL ; THE WILD MAGNOLIAS
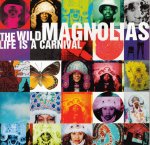
- Pock-A-Nae
- Coochie Molly
- Who Knows
- Life Is A Carnival
- Party
- Old Time Indian
- All On A Mardi Gras Day
- Shanda Handa
- Cowboys And Indians
- Black Hawk
- Pocket Change
- Herc-Jolly-John
- Buttlefield
- Hang Touch
- Tootie Ma
- Peacepie
METRO BLUE 7243 8 23737 2 81998年の初夏から盛夏にかけて、最も僕の車の中で流れたCD。いわゆるニュー・オーリンズのブラック・インディアン・トライブの代表格、ボー・ドリスとモンク・ボードルー率いるワイルド・マグノリアスの、正にマルディ・グラの熱気を伝えるアルバムだ。ジャケットもいつもながら派手派手でインパクト充分!
N.O.のブラック・インディアン・トライブについては、ドクター・ジョンの自伝「フードゥー・ムーンの下で」に詳しいが、そのドクター・ジョン自身が曲を提供、参加している。また、タイトル曲はザ・バンドの名曲のリメイクで、ロビー・ロバートソン、レヴォン・ヘルム、リック・ダンコ(合掌)が参加している。
(7)はギターの山岸潤二のプロデュースで、日本のブラック・ボトム・ブラス・バンドが参加、さらに、シリル・ネヴィルやネヴィル・ブラザーズ、ダヴェル・クロフォード、アラン・トゥーサンの名も見える。正に現在のN.O.FUNKを代表するアルバムとなった。
曲はセカンド・ライン・ファンクのオン・パレード!フル・ボリュームで身体をゆだねていると、トランス状態になりそうな乗り。理屈抜きに楽しめる。99年夏の来日は仕事で見逃した!非常に悔しい!だから今夜もこのCDかけながらサイクル・マシーンこいで減量に励もう!
SPIRIT OF NEW ORLEANS - THE GENIUS OF DAVE BARTHOLOMEW DISK 1
- Ain't Gonna Do It ; Dave Bartholomew
- Don't Marry Too Soon ; Jewel King
- Shrewsbury Blues ; Tommy Ridgley
- Stack-A-Lee ; Archibald
- The Blues Jumped Over The Rabbit ; Joe Turner
- Blow Your Top ; Rodney Harris & Dave Bartholomew
- 3X7=21 ; Jewel King
- Little Girl Sing Ding A Ling ; Dave Bartholomew
- I'm Gone ; Shirley & Lee
- Pony Tail ; T-Bone Walker
- Blue Monday ; Smiley Lewis
- I Got Booted ; Little Sony Jones
- I-Yi ; The Hawks
- Ain't It A Shame ; Fats Domino
- Thinking About My Baby ; Little Booker
- Every Dog Has A Day ; Pee Wee Crayton
- You Ain't So Such A Much ; Blanche Thomas
- Why Fool Yourself ; Bernie Williams
- Single Life ; Billy Tate
- The Real Thing ; Shirley & Lee
- Drops Of Rain ; Al Reed
- Mighty Long Road ; Joan Scott
- Teen Age Baby ; T-Bone Walker
- Bo Weevil ; Fats Domino
- Runnin' Wild ; Pee Wee Crayton
DISK 2
- Jump Children ; Dave Bartholomew
- Can't See For Lookin' ; The Hawks Featuring Dave Bartholomew
- Doin' The Hambone ; Little Booker
- Toy Bell ; The Bees
- I Hear You Knocking ; Smiley Lewis
- Witchcraft ; The Spiders
- Nothing Sweet As You ; Bobby Mitchel And The Toppers
- Valley Of Tears ; Fats Domino
- Hoo Doo ; Al Reed
- Morning Star ; James "Sugar Boy" Crawford
- Let The Four Winds Blow ; Roy Brown
- Sick And Tired ; Chris Kenner
- Good News ; Dave Bartholomew
- I'm Gonna Be A Wheel Someday ; Bobby Mitchell
- One Night ; Smiley Lewis
- Young School Girl ; Fats Domino
- She's Got A Wobble (When She Walks) ; James "Sugar Boy" Crawford
- I Walk In My Sleep ; Berna-Dean
- Come On -pts.1&2 ; Earl King
- I Wanna Know ; Al Robinson
- That Certain Door ; Ford "Little Snook" Eaglin
- Walking To New Orleans -undubbed version ; Fats Domino
- Little Willie ; Berna-Dean
- Trick Bag ; Earl King
- They Said It Couldn't Be Done ; Al Robinson
EMI 0777-7-80184-2 1「ニューオーリンズの魂」デイヴ・バーソロミューがプロデュースした、インペリア時代の2枚組コンピレーション。10年近く前の盤なので、ちょっと手に入れにくいかもしれないが、見つけたら即買いして損はない。いかにもリイシューといったジャケット写真もいかしている。下段の写真はブックレットから。ファッツ・ドミノと談笑している。
バーソロミューはファッツ・ドミノとの仕事でよく知られており、この中にも何曲か取り上げられているが、けっこう渋い選曲である。T-ボーンとかピー・ウィーとかいったテキサス〜ウエスト・コーストのギタリストも、バーソロミューのマジックにかかると、N.O.しちゃうから不思議だ。この、少しふわふわと跳ねるようなリズムは、虜になると仲々脱けられない。
いくつか気付いた曲について見ていこう。まず、アーチーボルドの「スタッカ・リー」、有名な伝承曲なんだが、このピアノ、ミッシェル・ポルナレフの「ラヴ・ミー、プリーズ・ラヴ・ミー」に似てません?けっこうポップなんだよね。それからバーソロミューの「リトル・ガール・シング・ディング・ア・リング」と、ザ・ビーズの「トイ・ベル」、同じ曲(こどものはやし歌のようなもの。ちなみにディング・ア・リングはおちんちんのことで、歌詞の中のヨーヨーは玉のことだ)で、こんなの出しちゃうんだもん。好きだなぁ。この曲は後にチャック・ベリーがロンドン・セッションで取り上げ、シングル・カットしたら全米1位になった。これがチャック唯一のポップ・チャートNo.1なんだから、なにが流行るか分からないものだ。
現在もブラックトップでレーベル・メイトなのが、アール・キングとスヌークス・イーグリンだ。アール・キングの「カモン」は「ダーリン・ハニー・チャイルド」(または「レット・ザ・グッド・タイムズ・ロール」)の再録で、ジミ・ヘンドリックスが取り上げてロック畑でも有名になった。トリック・バッグはセカンド・ライン・ファンクの古典と言える曲だ。スヌークス・イーグリンは本名を Fard Eaglin といい、フォードは「Fard などという綴りはあり得ない」と、勝手につけられたんだそうだ。この時代は一方でストリートの弾き語りの録音を、フィールド・レコーディングを受ける形で残しているが、このバンドスタイルの方が断然いい。単独盤も出ており、「トラヴェリン・ムード」なんて曲は最高だ。
ニューオーリンズのリズムの跳ねとユルさ、この際みんなで中毒になろう!
ROCKIN' PNEUMONIA AND THE BOOGIE WOOGIE FLU ; HUEY "PIANO" SMITH Bobby Fields
Bobby Marchan
- Give A Helping Hand
- Pitty Poor Me
Huey "Piano" Smith & The Clowns
- Chickee Wah Wah
- Don't Take You Love From Me
- I'll Never Let You Go
- I Can't Stop Loving You
- You Can't Stop Her
- Rockin' Behind The Iron Curtain
- Hash Your Mouth
Bobby Marchan
- Rockin' Pneumonia And The Boogie Woogie Fru Pts. 1 & Pts. 2
- Just A Lonely Clown
- Free Single And Disengaded
- I Think You Jiving Me
- High Blood Pressure
- Don't You Just Know It
- Havin' A Good Time
- We Like Birdland
- Don't You Know Yockomo
- Well I'll Be John Brown
- Dearest Darling
- Tu-Ber-Cu-Lucas And Sinus Blues
- Tiddley Wink
- Loberta
ACE/P-VINE PCD-2474ドクター・ジョンに多大な影響を与えたピアニストでバンド・リーダーのヒューイ・スミス(ジャケット写真を見ると、結構「スリム」で格好いい)と、彼のバンドで「女声」のメイン・ヴォーカルをとっていたボビー・マーチャンの1950年代後半の ACE 録音集。元々「ドラッグ・クィーン」(女装した男性歌手)として活動していたらしいボビーは、1955年に ボビー・フィールド名義で ACE に初録音する。その後ヒューイ・スミスのバンドに加わって、ニューオーリンズ・クラシックともいうべき(10)や、ポップスのトップ10ヒットの(15)(レーベル・オーナーのジョニー・ヴィンセント名義の発売もあったようで、かなりもめたようだ)、「高血圧」(ライナーによると、マリワナなどでハイになった状態のスラング)(14)など、スミスのバンドのわいわいがやがやした楽しい曲でリードを取る。スミスは50年代ニューオーリンズを代表するピアニストで、先に述べたドクター・ジョンの他、アラン・トゥーサンにもその影が見える。スタイルはプロフェッサ・ロングヘアと同様きわめて音数の多い明るいピアノだが、バンドの中で、典型的なセカンドラインとでも言うべき、より跳ねるリズムが特徴だ。しかしスミスの重要な面は、バンド・リーダーとして、ユニークな音楽作りをしたことだろう。ある面ジョニー・オーティスや後のジョージ・クリントンなどのような役割を果たしていたといえよう。一方ボビーはスミスのバンドでのヴェルティな歌と同時に、(5)や(6)のような自己名義では、R&B 歌手としても相当な力量を持っていることを伺わせる。もっと注目されていい歌手だ。
こんな素晴らしい才能を持っていたスミスだが、60年代になると大きなヒットにも恵まれず、酒に溺れていく。そして信仰によって立ち直った後は、二度と歌わないと決心したようだ。なんとも惜しいことだ。
THOSE LONELY, LONELY NIGHTS ; EARL KING 
- A Mother's Love
- I'm Your Best Bet, Baby
- What Can I Do
- 'Till Say Well Done
- No One But Me
- Eating And Sleeping
- Sittin' And Wonderin'
- Funny Face
- Those Lonely, Lonely Nights
- My Love Is strong
- Little Girl
- It Must Have Been Love
- I'll take You Back Home
- Mother Told Me Not To Go
- Is Everything Alright
- Those Lonely Lonely Feelings
- You Gonna Fly High
- Well 'O Well 'O baby
- I'll Never Get Tired
- Everybody's carried Away
- Buddy It's Time To Go
- Don't You Know You're wrong
- Everybody Got To Cry
- Darling Honey Angel Child
- I Can't Help Myself
P-VINE PCD-2478現在も現役で活躍するアール・キングの1950年代後半の録音集。(1)〜(8)が SPECIALITY、(9)〜(25)がそのA&R マンであったジョニー・ヴィンセントが興した ACE での録音となっている。バックのピアノは前半はヒューイ・スミス、後半はジェームズ・ブッカーが担当している。ギター・スリムの「代役」として売り出し中だったアールの1954年録音(1)などを聴くと、モロにギター・スリムの影響を受けているのが分かるが、スリムよりユルい持ち味が徐々に出てくる。「ニューオーリンズ三連」ともいうべきスロー・ナンバーとロッキン・ナンバーの両方で味のある歌とギターを聴かせる。また、ソング・ライターとしての才能が素晴らしく、ジョニー・ギター・ワトソンの取り上げた(9)は名曲だ。スヌークス・イーグリンも(10)などアールの曲を多く取り上げている。そして特筆すべき曲はなんといっても(24)だ。後に IMPERIAL で「カモン」として再録したこの曲、ジミ・ヘンドリックスが取り上げてロック畑にも有名になったが、これぞ真にニューオーリンズ・フォンクのもっとも初期のもののひとつと言えるのではないだろうか。 ACE を離れたアールは IMPERIAL で録音を続け、先の「カモン」の他、「トリック・バッグ」という重要曲も残している。しかし IMPERIAL 時代をまとめた単独 CD は出ていないようだ。TOSHIBA さん、ぜひ出して欲しいなぁ。それから BLACK TOP からの新譜、出ないかなぁ。ちなみにこのジャケット写真、第1回ブルース・カーニヴァルの時のものだと思う。
DR. JOHN'S GUMBO 
- Iko Iko
- Blow Wind Blow
- Big Chief
- Somebody Changed The Lock
- Mess Around
- Let The Good Times Roll
- Junko Partner
- Stack-A-Lee
- Tipitina
- Those Lonely Lonely Nights
- Huey Smith Medley
- High Blood Pressure
- Don't You Just Know It
- Well I'll Be John Brown
- Little Liza Jane
ATCO/EAST WEST AMCY-3041ドクター・ジョンことマック・ルベナックが1972年に発表した、自分のルーツである「古き良き時代のニューオーリンズ・ミュージック」が世に広がることを願って作ったアルバムだ。「JFK」で有名なギャリソン判事がニューオーリンズ(以下N.O.と略す)に赴いて以来、「良き時代は終わった」と、カリフォルニアに拠点を移していたドクター・ジョンは、N.O.時代のスタジオ仲間で大先輩である、AFOレーベルのハロルド・バティステをプロデューサー(もうひとりはATLANTICのジェリー・ウェクスラー)に迎え、メルヴィン・ラスティエ、リー・アレン、アルヴィン・ロビンソンらN.O.名うてのミュージシャンを集めて、彼の地のクラシックともいうべき名曲の数々をよみがえらせた。アルバムにはドクター・ジョン自身がそれぞれの曲のオリジナルに対する、自身の体験を含めたコメントが添えられていて、このアルバムの趣旨をより明確にしている。取り上げた曲はドクター・ジョンが敬愛してやまないプロフェッサー・ロングヘア(通称「フェス」)、ジョニー・ヴィンセントのACEでレーベル・メイトだったヒューイ・スミス、アール・キングのものの他、N.O.の伝承曲と云うべきものもあり、まさに「ガンボ」(ごった煮)となっている。
まずは(1)「アイコ・アイコ」、この曲はN.O.のガール・グループ、ディキシー・カップス(「チャペル・オヴ・ラヴ」のヒットで有名)が1965年にリメイクしてヒットさせたものがよく知られているが、元々はN.O.のブラック・インディアン・トライブ(マルディ・グラなどの際、黒人がインディアンの扮装をして路上でパーカッシヴな演奏を繰り広げるグループ)のチャントであり、「スパイ・ボーイ」など、それを伺わせる歌詞が出てくる。オリジナル・ヒットはジェームズ・シュガーボーイ・クロフォードが「ジャコモ」のタイトルでCHECKERから出したものだ。ドクター・ジョンはこのルンバ調のリズムの曲をボー・ディドリー的なアタックの強いアレンジにしており、セカンド・ライン・ビートの効いたピアノが印象的だ。コーラス、ホーン・アレンジとも、見事なポップ・チューンに仕上げている。久保田麻琴はこのヴァージョンの影響を受けているようだ。珍しいところではウルフルズが「大阪ストラット」のケツでパクっている。
(8)「スタッカリー」も古くから歌われている伝承曲で、ロイド・プライスが「スタッガリー」として大ヒットさせたものが有名だが、これは1951年のアーチーボルドのヴァージョンをベースにしている。ドクター・ジョンが弾く原曲にほぼ忠実なきらびやかなピアノが印象的だ。ちなみにこの曲、アーチーボルドのオリジナルは2パートに分かれており、パート2はピアノで始まるが、これがミッシェル・ポルナレフの「ラヴ・ミー、プリーズ・ラヴ・ミー」とそっくり!コード進行などを考えても、ポルナレフがこの曲にインスパイアされた可能性もあると思うが、いかがだろうか。
伝承曲と云えば(7)「ジャンコ・パートナー」も古くからN.O.に伝わる曲で、「ジャンコ」とは元来は囚人、放蕩者を意味するそうだが、明らかに「ヤク中」とのダブル・ミーニングだ。ドクター・ジョンはロールを多用するドラムなど、思いっ切りセカンド・ラインしたアレンジで、N.O.の古き良きギャンブル、売春などを懐かしむように奔放に歌っている。ホーン・アレンジは典型的なコズィモ・スタジオ〜AFOスタイル(ティファナ・ブラスに影響を与えたという)で、このアルバムの中でもN.O.臭を強く感じさせる。この曲については、ドクター・ジョンの「ヤクダチ」(まさにジャンコ・パートナー!)ジェームズ・ブッカーの弾き語りがマストだと思うが、フェスのヴァージョンも捨てがたい。1961年にリリースされたローランド・ストーンのACEへの吹き込みには、ドクター・ジョン自身も絡んでいる。
そのフェスだが、レイ・チャールズがオリジナルのピアノ・ダンス・チューン(5)「メス・アラウンド」も彼が好んで取り上げた曲だ。カウ・カウ・ダヴェンポートの「カウ・カウ・ブルース」にルーツを持つこの曲、ドクター・ジョンは「カウ・カウ・ブルース」のポール・ゲイトゥンがカヴァーしたものに強い影響を受けている。自分のピアノを軸にしながら、やはりセカンドラインするドラム、リフを強調するホーン・アレンジなど、モダンで楽しい。N.O.のクラブでは毎夜こうしたご機嫌なナンバーで踊り明かせたんだろうなぁ。一方(9)「ティピティーナ」はフェスの代表曲と言ってもいい8小節のブルースで、曲そのものはN.O.でよく聴かれるもの(例えばチャンピォン・ジャック・デュプリーの「ジャンカー・ブルース」など)だが、オリジナルよりさらにテンポを落とし、フェスの気怠そうな歌い方をより強調したドクター・ジョンの弾き語りは、この曲の持つアンニュイな魅力をうまく引き出していると思う。
(3)「ビッグ・チーフ」(大酋長)もブラック・インディアンの伝統を受け継ぐマルディ・グラ・ソングだ。オリジナルはフェスのピアノとスモーキー・ジョンソンのドラム、それにゴージャスなブラスバンドをバックに、アール・キングが口笛と歌を聞かせる2パートにわたる大作だ。フェスのセカンド・ラインの効いたリフが特徴的で、フェス自身も何度も再録している。ロニー・バロンがこのリフをパイプ・オルガンの音色で弾きこなすアレンジは、途中のコーラスの使い方とあいまって、エキゾチックなムードを醸し出している。
上の曲の作者であるギタリスト、アール・キングの曲も2曲取り上げられている。まず(6)「レット・ザ・グッド・タイムズ・ロール」はルイ・ジョーダンの曲とは同名異曲のN.O.クラシック・ファンクとも言うべきで、ACE時代「ダーリン・ハネー・チャイルド」の名前でもリリースされている。ドクター・ジョンがベースにしたのはIMPERIAL時代の再録で、こちらは「カモン」のタイトルで2パートに分けて出され、ジミ・ヘンドリックスがカヴァーしてロック畑でも有名になった曲だ。ドクター・ジョンはディストーションの効いたギターを自ら弾き、テンポを落としてセカンド・ラインを強調、コーラスとアラン・トゥーサンを思わせるアレンジのホーンを加え、ファンクネスを感じる仕上がりにしている。ロック・ファンにとって魅力的なアレンジで、30年近くたった今聴いても色褪せていないのはさすがだ。もう1曲は典型的な8小節のルイジアナ・バラード(1)]「ゾーズ・ロンリー・ロンリー・ナイツ」だ。僕はこの曲が個人的に大好きなんだが、オルガンなどを加えながらもほぼオリジナルに忠実にやっていて違和感がない。ピアノ・ソロでブレークが入るのがアクセントになっているが、アルヴィン・ロビンソンのギター・ソロもオリジナルを忠実に模していてほほえましい。
さて、本アルバムの中でもっとも多く取り上げられていると言えるのが、ヒューイ・ピアノ・スミスだ。ドクター・ジョン自身の言葉によれば、彼にN.O.のショー・ビジネスのイロハを教えてくれたピアニスト=バンマスで、よく転がるピアノとノヴェルティな歌・コーラスのダンス・チューンを50年代後半にヒットさせた、N.O.ではとりわけ人気の高いミュージシャンだが、このアルバムが出されたころには完全に引退(庭師をやっていたという)してしまっていた。(11)「ヒューイ・スミス・メドレー」はそんな彼のACE時代の代表作を3曲つないだもので、オリジナルではボビー・マーチャンらの「オカマ」歌とコーラスを中心にしたコミカルな曲の数々を、ドクター・ジョンはゆったりとしたシャッフルに仕立て、のどかなムードを醸し出している。なんだかスタジオでみんなで楽しく遊んでるって感じで心地よい。
(2)「ブロウ・ウィンド・ブロウ」のオリジナルはジュニア・ゴードンで、ドクター・ジョン自身のライナーを読むと、1955年ごろスパイダーズ名義で吹き込んだとされているが、そのゴードンが1956年ヒューイ・スミスのバンドをバックに録音したカリプソの香りがするヴァージョンがよく知られている。ドクター自身もヒューイ・スミスのピアノを意識して弾いている(特に後半のブレークの部分にそれを感じる)ということだ。ゆったりしたセカンド・ラインに乗って、トロピカルな香りのする作品に仕上がっている。古いフォークソングがもとになっている(12)「リトル・ライザ・ジェーン」もヒューイ・スミスのバンドをバックにジュニア・ゴードンが吹き込んだものをベースにしたようだ。こちらもテンポを落としているが、リー・アレンのサックス・ソロ(ユーモレスク!)はオリジナルにかなり忠実、ラストを飾るにふさわしい楽しいナンバーだ。
ドクター・ジョンがこのアルバムに収録した唯一のオリジナル(4)「サムバディ・チェンジド・ザ・ロック」は、ディキシーランド・ジャズの香り高い小品だ。1962年AFOの傍系レーベルにロニー・バロンと「マイ・キー・ドント・フィット(サムバディ)」のタイトルで吹き込んでいる。弾き語りをベースにしたようなリラックスしたピアノと歌に、コルネット、クラリネット、トロンボーンが絡み合って良いムード。
「Good Old Music」この言葉をドクター・ジョンがキーワードにして本アルバムをリリースして30年が経とうとしている。時代は流れ、本アルバムを含む70年代のN.O.ミュージック自体が現在「Good Old Music」として聴かれるようになった。伝統の橋渡しをしようとしたドクター・ジョン自身が、その伝統の一部になろうとしている。しかし今改めて聴き直し、現在の耳で捕らえたとき、このアルバムは少しも色褪せていない。紹介されている曲のオリジナルは確かにセピア色だが、このカヴァーはまだまだコントラストを失っていない。この「新しさ」がドクター・ジョンの魅力なのだと思う。最近録音された(本人の再録も含む)50〜60年代N.O.ミュージック集を何枚か聴いたが、懐古趣味(それはそれで良いのだが)の域を出ていなかった。そうした色合いを感じさせないところに本アルバムの魅力がある。そしてここを糸口に、セピア色の深い洞窟に「Good Old Music」を探しに旅出てほしいというのがドクター・ジョンの今も変わらぬ願いなのではないだろうか。
付記
本稿を書くにあたって、「The Roots Of Gumbo 〜 The World Of Dr. John」(P-VINE PCD-2820)の音および文屋章さんのライナーを参考にした。収録曲の多くが直接カヴァーの対象となったヴァージョンであり、あわせてお聴きになられることを薦める。ただし「ティピティーナ」はオリジナルのATLANTICのものではない1977年のライヴ・ヴァージョンであり、また、「ビッグ・チーフ」はpart 2のみ収録されている。
本文に記したように、本アルバムで取り上げられた曲には多数のカヴァー、別ヴァージョンが存在している。これらを芋弦を手繰るように探しながら聴いていくと、いつしかN.O.ミュージックを俯瞰できるようになると思う。また、ドクター・ジョンの自伝「フードゥー・ムーンの下で」(B.I.プレス)には、本作品に限らず、ドクター・ジョン、あるいはN.O.のミュージック・シーンについての興味深い話が満載されている。ぜひご一読されたい。
最後にジャケットの背景となっているフリスコ、おそらく2重になっているのだが、どこのものだろうか。こういうのを見つけにアメリカを旅するのもおもしろいかもしれない。おそらく現存していないとは思うが...
*本稿は、lyleさんのサイト「Paradice & Lunch」に寄稿したものに加筆・訂正したものです。
ZIGABOO.COM ; ZIGABOO MODELISTE 
- Shake What You Got
- Sing Me A Song
- Funky Nasty Cigarettes
- ZIG Me
- Standing In Your Stuff
- Tea Pot
- Gonna Have A Party
- My O' My What A Wedding Day
- K-9
- Black On Black Crime
- Nanny Goat Cheese
JZM 2001
一時は引退してL.A.で商売でもしているのではと言われていた、ミーターズの名ドラマー、ジョゼフ・”ジガブー”・モデリステがこの世紀末になって、全曲オリジナルの新作を引っ提げて帰ってきた。録音は主にサンフランシスコのようだが、出てくる音はまさにニューオーリンズだ。
頭の2曲を聴いたときは、「あれ」って感じだった。妙に軽いリズムとベースの、ちょっと古くさいブラコン風の(1)、腑抜けのネヴィルズみたいな(2)を聴いて、肩透かしを受けたような気分だった。ところが(3)のミーターズ風のロックンロールから、そのムードは一転!ちょっとこもった録音のドラムの音はジガブーそのものだったし、ちょっとお茶目なヴォーカルも魅力たっぷり。ミーターズの曲としては異色だった「ゼイ・オール・アスクト・フォー・ユー」を思わせる(8)も、楽しいパーティソングで、こういった「遊び」はジガブーの趣味だったのかななんて思ってしまう。ジャケットの「気のいいおっさん」風の表情を見ても、楽しんで作ったのがよく分かる。
(4)のインストは初期ミーターズに通じるセカンドライン丸出しのドラミング(ちょっとリハビリ不足な感じはしたが)に、ロック風のギターが絡む曲で、このアルバムを聴く前に一番期待したタイプの曲だった。ベースが付いていききれないのは仕方がないかな。犬の遠吠え風の声(こういう擬音、ジガブーは好きだよな)から始まる(9)も初期ミーターズの「イェイ・ユア・ライト」によく似たリフのアップ・ナンバーだが、すかすかではなく、ジガブーのタイトな中にちょっと遊びを感じるドラミングの上で、キーボード、ブラスが音を埋めていく。
このアルバムの中で僕の一番のお気に入りは、きゃっちーなリフを持つインスト(6)だ。初期ミーターズのいいとこ取りをして、21世紀に向けて「まだまだやるぜ」と宣言しているような気持ちのいい曲で、しばらくリフが耳から離れなかった。(11)は70年代終盤から80年代初めにかけての、ジャズとファンクを融合(まさにフュージョン)したタイプのインストで、この手の曲も最近あまり耳にしなかったので妙に新鮮に感じた。
残りはファンクネスを感じる歌もので、ミーターズ風の(5)(ただしベースがスラップ丸出しなところがジョージとの違いだが)、途中「ピック・アップ・ザ・ピーセズ」のようなブラスの決めが入る軽快なダンス曲(7)、同様にブラスがかっこよく絡み、ジガブーのチャーミングな唄い口が全開の(10)と、魅力的な曲が並ぶ。
このアルバム、何か新しい世界を切り開こうという感じより、ちょっと前の忘れられがちなファンク、ロックなどの曲を楽しくよみがえらせようという雰囲気を持っている。根底にあるのはニューオーリンズの「ガンボ」的な音楽の楽しみ方。ジガブーは20世紀の集大成として、すばらしい贈り物を届けてくれた。
MARVA ; MARVA WRIGHT 
- I'm Still Wearing Your Name
- Difficult Woman
- Love Away The Pain
- Let Them Talk
- The Weight
- Rockin' Pneumonia
- I Been Hoodood
- You've Been Partyin' All Night
- The Maker
- Save Somebody
- Knocking On Heaven's Door
- You Broke A Beautiful Thing
- Guess Who
- Cabbage Alley (Bye Bye Baby)
AIM 5010 CD
ニューオーリンズ屈指の女性シンガー、マーヴァ・ライトの自身の名前を冠した新作は、山岸潤史が全面的にプロデュース、すばらしい作品となった。ジャケットからも伺える豊満な身体と、ゴスペルで鍛えられた喉から発せられる、ふくよかで伸びのあるヴォーカルは、やはりバラードでその真価を発揮する。(1),(2),(3),(4)とタイプの異なるミディアム〜スロー・バラードの怒濤の連続攻撃はまさに圧巻で、圧倒的な声量と確かな、しかし技巧に走りすぎない唄い回しで、聴く者をぐいぐい引き込んでいく。これらの曲で山岸のギターは、決して出しゃばらず、しかし要所を締めた好サポートで、楽曲を完成度を高めている。特に(2)のアコースティック・ギターの使い方は秀逸だと思う。
ザ・バンドの名曲(5)は、「The Last Waltz」に収録されたステイプルズのヴァージョンを彷彿させる仕上がりで、ボー・ドリスなどとの絡みもあり、実に「濃い」一曲となっている。続く(6),(7)はニューオーリンズ・チューンで、前者はご存じヒューイ・スミスの代表的ロッキン・ナンバーで、セカンドライン・ファンクというべきリズムに、クールでジャジーなサックスが絡むモダンなアレンジがいかしている。後者はドクター・ジョンが「In The Right Place」で取り上げたミステリアスなムードを持つナンバー。マーヴァは原曲のイメージを活かしながら、張りのある声を駆使しつつ、重厚な作品に仕上げている。(8)はちょっと軽めのミディアムなソウル・ナンバー、続くはTerrance Simien(テレンス・サイミーン?)のヴォーカルをフューチュアした、アコーディオンとセカンドラインしたドラムズが、いかにもルイジアナっていう雰囲気で、この辺はちょっと息抜きって感じかな。リラックスしていて心地よい。
(10),(11)とボブ・ディランの曲が2曲続く。前者は原曲を聴いたことがないので比較ができないが、低重心の濃厚なミディアム・ロック・ナンバー。ゴスペル・フレィヴァー溢れるマーヴァのヴォーカルが見事にマッチしたか佳曲だ。後者は改めて言う必要もないほどの有名曲。レゲエ・タッチの軽妙なアレンジながら、ここでもマーヴァのゴスペル魂が曲をぐっと引き締めている。クライマックスはやはりお得意のバラードをじっくりと歌い上げる。哀愁の漂うゴスペル調バラード(12)、そして山岸の奏でるイントロが印象的なスタンダード(13)で、マーヴァは存分にその歌唱力を聴かせてくれる。やはりこうしたバラードでは真に「水を得た魚」だ。
ラスト(14)、クレジットはミーターズの面々になっているが、原曲はプロフェッサ・ロングヘアのマルディ・グラ・ソング「ヘイ・ナウ・ベイビー」、アレンジはミーターズの表題曲を踏襲したセカンドライン・ファンク。ボー・ドリスとのヴォーカルの絡み合いは、自分の足場がニューオーリンズにあることを高らかに宣言しているようだ。
ゴスペルとニューオーリンズというマーヴァの二つのルーツを程よくミックスした本作は、彼女の代表作と言ってよいのではないだろうか。アルバム構成上はややバラードが多く重たい感じになり、もう少しアップナンバーがあってもとも思うが、マーヴァの特性を考えたら止むを得ないところだろう。じっくりとしたヴォーカルを聴きたい人には絶対のお薦めの一作だ。
WHAT ABOUT THE PEOPLE ; SMILIN' MYRON 
- Johnny
- Tuna Ritz
- Horace Greedy
- The Marcsman
- The Ole Pegan Trail
- Bruff Lady
- The Mouse
- Everyday
- Apple Juice
- Business, That Is Tom
SMILIN' MYRON no number
ニューオーリンズのファンク・ジャムバンドと言えば、真っ先にギャラクティックが思い浮かぶが、それと比べても遜色のないバンドが現れた。1997年の自主制作盤だが、完成度は極めて高い。P-VINEがボーナストラックをつけてリリースするのも頷ける。
アルバムはシンメトリーに曲が配置されている。まず(1)はどっしりとしたファンクネス溢れるリズムにジャジーなホーンが絡む。ティム・ガーリスコの決して上手くはないけど粘っこい歌で、「ジョニー」のテーマのリフレインはなぜか耳に残る。裏のユニゾンの絡みが格好いいからだろう。ティムのギター(おそらくセミホロウ)はリードだけでなくバッキングのコードプログレッションでも暑苦しさを演出している。続く(2)はラテンビートにのって、ティムがアコースティックを弾くが、パーカッションとの見事な絡み合いで、実に生き生きとしている。ミュートの効いたマーク・マリンズのトロンボーンも心地よい。これと同様のパーカッシヴなラテン系ギター・インストがラス前の(9)で、プピ・メネスのパーカッションが大活躍。途中ホーンによるリフをはさんで、洒落たトロンボーンのソロへ。いろいろな音楽をバックボーンに持つメンバーが集まって、まさにジャムってるって感じ。
(3)と(8)はヴォーカル入りのファンク。(3)はオンビートの効いたロック色を感じる曲で、ごにょごにょとしたティムの歌がなぜかマッチする。転調しながらのサックス・ソロはJB'Sを彷彿させる。タイトなホーンリフをバックにしたサム・ホチキスのギターはアバンギャルドだ。重心の低い(8)でもサムのギターは相変わらず自由奔放。途中のユニゾンの決め、このバンドがジャムバンドとして相当な技量を持っていることが分かる。転調するとまたまたJB'S風のややジャズ・フレイヴァの効いたファンクに。エリック・トラウのサックスがジャズっぽさを醸し出すが、安っぽいジャズ・フュージョンとはバンドの重心がまるで違う。
(4)と(7)はインストの小品。(4)はギターのコードリフで始まるややアップテンポなファンク。アンドレアス・アージェンティのドラムはギャラクティックのスタントン・ムーアほどファットバックではないけれど、プピのパーカッションと絶妙に絡みながら、しっかりとした重心の低いリズムを打ち出してくる。一方(7)は2本のギターが交差するような細かいリフをテーマにしたアップテンポのファンク。ここでの聴きものはマーク・ペロのベースソロ。ややブーストした高音部で自在に弾きまくる。とにかくドライヴするバンドが快感!
真ん中の2曲がカントリー調というのがこのバンドの一筋縄でいかないところだ。(5)は何と地虫だかカエルだかの泣き声をバックに、生ギターをバックに皆で小唄をラフに唄う。ちょっとしたお遊びだけど、こういうの好きだな。そしてほぼメドレーのような感じでトゥービートのブルーグラスっぽいカントリー曲(6)に突入。コーラスもけっこうさまになっていて、これにバンジョー、フィドルでもかませたら田舎のダンスパーティって感じだ。ティムのギターがかなり達者で聴かせる。
さてラストの(10)はセカンドライン風のドラムにのって、ギター・ベースがどろっとしたファンクを展開する。ティムのギターは相変わらず粘っこい。そして電話のコール音と、それに答える台詞で幕を閉じる。このまま1曲目にオートリピートすると、もう完全にスマイリン・マイロンの無限ループに突入だ。とにかくスリーブのイラストのように、さまざまな要素をまぜこぜにして皆まとめて楽しんじゃおうというバンドの姿勢がよくあらわれている作品だ。久々に立て続けに3回も聴いてしまった。
その後P-VINEから邦盤がリリース(PCD-24073)され、次の2曲がボーナスとして収録された。そのライナーによると、サウンド作りの要のギタリストだったティムが、実はこの作品のリリース直前ににガンで亡くなっており、メンバーチェンジしているようだ。
- Got To Privide
- Hoochy Kooch
ボーナスはいずれも地元ニューオーリンズのメイプル・リーフ・バーでのライヴで、(11)は2001年5月のジャズ・フェス中の演奏。12分を越える長尺のジャムで、ブルージーなギターリフにのって展開される。ベースソロは圧巻。(12)はホーンの効いた2001年2月の演奏。いずれも録音はあまり良くないが、内容は悪くない。でもこのボーナスを収録したことにより、オリジナルアルバムの統一感がかなり損なわれたことも事実だ。もしP-VINE盤(こちらの方がはるかに入手しやすい)を入手されたら、この2曲をスキップしてリピート再生してみることを薦める。
HOME ・ INDEX ・ BLUES ・ SOUL/FUNK ・ ROCK


