ロックのCD
HOME ・ INDEX ・ BLUES ・ SOUL/FUNK ・ NEW ORLEANS
RAISIN' HELL ; ELVIN BISHOP 
- Raisin' Hell
- Rock My Soul
- Sure Feel Good
- Calling All Cows
- Juke Joint Jump
- Hey, Hey, Hey, Hey
- Joy
- Stealin' Watermelons
- Fool Around And Fell In Love
- Little Brown Bird
- Yes Sir
- Struttin' My Stuff
- Give It Up
- Travelin' Shoes
- Medley(Let The Good Times Roll / A Change Is Gonna Come / Bring It On Home To Me)
CAPRICORN 314 558 395-2エルヴィン・ビショップの1976〜8年のライヴ。(多分)1999年に初CD化された。待ってました!
まず(1)のタイトル・インストがかっこいい!アップのシャッフルに乗って、けっこうトリッキーなフレーズを連発!ツイン・リードの決めがあったりして、ギター・フリークなら必聴の一曲。
ヴォーカルはエルヴィン自身(のどかな歌声で好き)の他、ミッキー・トーマス(スターシップ!とってもハイトーン)が参加。タワー・オヴ・パワーのホーン・セクションを加えた、ゴージャスな音作り。ディスコ全盛時代だが、16ビートの曲((4)や(12)など)は、それほどディスコっぽくなく、ファンキーな演奏が心地よい。(8)は名曲だ。
大ヒット(9)は、サザン・オールスターズの1st「熱い胸騒ぎ」に収録されていた、「お熱いのが好き」の元歌で、ミッキーが熱唱している。(10)はマディ・ウォーターズのスロー・ブルースで、エルヴィンのスライドがたっぷり聴ける。ラスト二曲は圧巻で、特にサム・クックのメドレーは盛り上がる。こんな名盤がなぜ日本盤で出ないのかが不思議。見つけたら即買いの1枚。なお、このアルバムのジャケットでおかしいのは、観客席にエルヴィンの等身大の看板が掲げられている(小さいのでちょっと分かりにくいが、右の方の高くなった白い点の部分が帽子)ことで、このエルヴィンの笑顔がまた素敵なのだ。
BO & GUMBO ; ボ・ガンボス
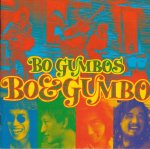
- 助けて!フラワーマン
- 泥んこ道を二人
- 魚ごっこ
- Hey Frower Brother
- ダイナマイトに火をつけろ
- 夢の中
- ずんずん
- 見返り不美人
- トンネルぬけて
- ZOMBIE-ZONB☆
- ワクワク
- 目が覚めた
EPIC/SONY 32・8H-5102こんな形でこのCDを紹介することになるとは思わなかった。2000年1月28日に、どんとは天に召された。大ファンというわけではないが、このCDとR.C.の「カバーズ」は僕にとって特別な作品だ。ジャケットもガンボしてるし。
ニュー・オーリンズ録音されたこのデビュー作、テンションが高い。どんとのラフでルーズで、でもハイテンションなヴォーカルと、KYONの泳ぎ回るギター、ピアノはフェス(プロフェッサー・ロングへアー)まるだしで、リズムのふたりがどっしりと、でも軽妙に固める、そんな感じだ。で、ニュー・オーリンズ・フレイヴァーはと言えば、パーカッションが凄い。シリル・ネヴィルにウガンダ・ロバーツと来れば、N.O.ミュージック・ファンにはたまらないだろう。その上(7)ではボー・ディドリー御大がギター・マラカスなどで参加している。このえらく直接的表現の歌を、これだけからっと演られちゃうと、楽しくなっちゃう。(1)や(5)のように社会批判やラディカルなテーマもあり、ロックしている。でも、ベストは魚ごっこだな。この歌、病みつきになるよ。百聞は一聴にしかず!でも売ってんのかなぁ?
"LIVE" FULL HOUSE ; J. GEILS BAND

- First I Look At The Purse
- Homework
- Pack Fair And Square
- Whammer Jammer
- Hard Drivin' Man
- Serves You Right To Suffer
- Cruisin For A Love
- Looking For A Love
ATLANTIC AMCY-146アメリカを代表するロックバンド(と僕は思っている)の、3枚あるライヴアルバムの最初のもの。1972年、バンドの地元デトロイトでの録音。このバンドのライヴアルバムはすべて良いが、これが最も初々しくて好きだ。ブルースをベースにしており、オーティス・ラッシュの(2)、地元のヒーロー、ジョン・リー・フッカーの(6)など、J.ガイルズの余分な音をそぎ落とした、ブルースのエッセンスを知り尽くしたギタープレイは聴き物だ。ピーター・ウルフのヴォーカルは、表情が豊かで、ちょっと大袈裟に聞こえるときもあるけど、凄くセクシー。フェイ・ダナウェイが参ったのも分かる気がする。(8)はボビー・うーマックとヴァレンティノズのヒットのカヴァーで、ガイルズの初ヒットともなった曲だ。しかし何といってもこのアルバムで最も有名なのは、マジック・ディック一世一代のハープ名演の(4)だろう。僕がこの曲をFENで聴いたときは正直ぶっ飛んだし、いまだに毎日かかっているそうだ。音質等は悪いけど、熱いアルバム。でも、ジャケットのカード、フルハウスじゃないんだよね。
WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS ; JOE COCKER
- Feeling Alright
- Bye Bye Blackbird
- Change In Louise
- Marjorine
- Just Like A Woman
- Do I Still Figure In Your Life?
- Sandpaper Cadillac
- Don't Let Me Be Misunderstood
- With A Little Help From My Friends
- I Shall Be Released
A&M 393 106-2しかし強烈なジャケットだ。タイトル通りジミー・ペイジ、スティーヴィー・ウィンウッド、アルバート・リーなどの一級のミュージシャンを集めて作られたこのアルバムは、一方で1969年という、時代の大きな変り目も映すものになった。パーカッションとピアノのバックがファンキーなトラフィックの(1)で始まるこのアルバムは、イギリス人達が作ったアルバムなのに、妙にアメリカの香りがする。ブリティッシュ・ロッカー達は60年代中ごろから、アメリカの特に黒人音楽に強く影響されたロックを次々と生み出し、ビートルズに代表されるようにアメリカに「逆輸出」していく。また、ストーンズやヤードバーズ、さらにはレッド・ツェッペリンなど、アメリカ黒人文化であるブルースを独自のスタイルに昇華させた音楽も生み出されている。アメリカ人ジミ・ヘンドリックスはイギリスで開花した。しかしこのアルバムは、よりアメリカの音楽に踏み込み、あたかもアメリカそのもののようですらある。
(4)や(7)などにやはりブリティッシュかといった香りはある。しかし(2)や(5)、そしてタイトル曲の(9)を聴くと、「これってブリティッシュ?」という想いが頭をめぐる。特にリンゴ・スターのある意味能天気な(9)が、ゴスペルティックなコーラスを伴うワルツにリメイクされたのは、真に別の曲になったといった趣だ。アメリカの1970年代を舞台にした青春物テレヴィドラマの主題歌に使われていたが、ぴったりはまっていたのを記憶している。そしてボブ・ディラン=ザ・バンドの(10)、大西洋の隔たりをまさに解き放った1作と言ったら、過大評価のしすぎだろうか。この翌年ジョー・コッカーは、アメリカで、「イングリッシュメン」と呼ばれるアメリカ人達とバンドを組む。
PHOEBE SNOW
- Good Times
- Harpo's Blues
- Poetry Man
- Either Or Both
- San Francisco Bay Blues
- I Don't Want The Night To End
- Take Your Children Home
- I Must Be Sunday
- No Show Tonight
- Easy Street
SHELTER 7243-8-31972-2-420年ほど前、当時行きつけの飲み屋でよくリクエストして聴いたアルバム。僕の青春の1枚だ(実は当時惚れてた女の子の横顔が、このジャケットに似ていた)。フィービ・スノウの声は、本来少しドスの利いた、決して透明感のあるものではないと思うが、このアルバムの音楽からは、彼女の声を含め、透明で瑞々しいものを感じる。日頃泥臭いブルースばかり聴いているせいかもしれないが。
まずサム・クックの(1)を、アコースティック・ギターによるブルース丸出しのボトム・リフで始める(CDにはLPではカットされていたカウントを取る声が収録されているが、ないほうが良い)。しかしベースのヒュー・マクドナルド、ドラムスのスティーヴ・モズレィのバックはあくまでクールで都会的だ。ゆったり目の歌も、サムのポップな曲調とは異なり、大人っぽさを感じる。(2)と(3)ではズート・シムズのムーディなテナーが効果的。特に(3)は名曲だ。サウンドに身をゆだねていると、フィービの声がスゥっと心の奥に染み入ってくる。大きめの音で、まどろみながら、目をつぶって聴きたい曲だ。(4)はデヴィッド・ブロムバーグのドブロが絡んだフォーク調の曲。そしてこれも名作(5)だ。ジェシー・フラー作の、フォーク・ブルース・ブームの時によく取り上げられた曲だが、この演奏と歌はあくまでジャジーでブルージー。バーのカウンターでブランデーでもくゆらせながら聴きたい曲だ。(7)も(3)に似た雰囲気で気に入っている。そしてオリジナル・アルバムのラストが、デイヴ・メイソンのギターが印象的なソフト・ロック(9)だ。なおCD化に際し10が追加された。
とにかく20才そこそこの時に、都会の大人のムードと、青春の切なさの両方を感じさせてくれた、僕にとっての永遠の必聴盤だ。今聴いても決して古臭くない。感性の豊かな若い人にこそ聴いてもらいたい。
TAPESTRY ; CAROLE KING 
- I Feel The Earth Move
- So Far Away
- It's Too Late
- Home Again
- Beautiful
- Way Over Yonder
- You've Got A Friend
- Where You Lead
- Will You Love Me Tonight
- Smackwater Jack
- Tapestry
- (You Make Me Feel Like) A Natural Woman
- Out In The Cold
- Smackwater Jack
ODE/EPIC ESCA 7770シンガー・ソングライターと聞いて、誰を真っ先に思い出すだろうか。キャロル・キングを思い浮かべる人も多いだろう。しかし彼女はシンガーである前にソングライターとして才能を開花させていた。生っ粋のニューヨーク娘であった彼女は、隣に住んでいたというニール・セダカに「オー・キャロル」と歌われるほどのチャーミングな女性だった。また、音楽的な才能も素晴らしいものがあり、リトル・エヴァの「ロコモーション」、ドリフターズの「アップ・オン・ザ・ルーフ」、そしてこのアルバムで自身も唄っているシュレルズの「ウィル・ユー・ラヴ・ミー・トゥモロウ」など、かつてのパートナーであったジェリー・ゴフィンとの共作で、ヒット曲を量産していた。特に注目すべき点は、ブラックのアーティストにも素晴らしい楽曲を提供していることで、(12)はアレサ・フランクリンの名唄でヒットしている。その彼女が1970年代に入って本格的な歌手活動を始めたのちの2作目が、この70年代を代表する名作「つづれおり」だ。アルバム・チャート15週トップで、1,500万枚(!)を売り上げたメガヒットであるが、この作品は宣伝やブームで売れたのではない。真に内容が人々の耳と心を捉えたのだ。
まずは代表曲(3)だ。当時中学生だった僕も、この曲のやや暗いイントロと、印象的なテーマ、歌詞の意味は当時よく理解できなかったけれど、何か深いところに響いたのを覚えている。これがアップテンポの(1)とのカップリングで全米1位となった。(2)は荒井(松任谷)由美に多大な影響を与えただろうバラードで、ロッド・ステュワートが敬意を持ってカヴァーしている。以前レガシーのコマーシャルに効果的に使われていたのがロッドのヴァージョンだと思う。(6)もきわめてソウルフルなバラードで、キャロルの作曲能力の高さを示す佳曲だ。そして名曲中の名曲(7)だ。このレコーディングにも全面的に参加しているジェームズ・テイラーが、ややアップでフォーク調のアレンジでこの曲をリリース、見事全米1位となっているが、このキャロルのオリジナル・ヴァージョンにはかなわないと思う。心に染み入る名曲で、僕の友人の英語教員は、この歌を教材にしていた。そしてこの歌はソウル〜ゴスペルのスタンダードとなっている。ロバータ・フラックのダニー・ハザウェイのデュオ、そのダニーのライヴでの名唄、そしてアル・グリーンの素晴らしいゴスペル・ヴァージョン。この歌が人種や時代を越えた、普遍的な愛の歌であることを見事に証明している。
シュレルズのセルフ・カヴァー(9)もテイラーの息のあったコーラスを得て、瑞々しい魅力に充ちている。クィンシー・ジョーンズもカヴァーしたポップな(10)に続き、タイトル曲(11)で人生を「つづれおり」に例える。そしてアレサとは違った意味での力強さをもった(12)で、アルバムは締めくくられる。一つ一つの楽曲と演奏の素晴らしさ、そしてトータルに構成されたアルバム・プロデュース。猫を配した優しさ溢れるジャケット。これはやはり歴史に残る名盤だ。(CD化に際し2曲のボーナスが加えられているが、僕には蛇足に思える。)
LEVEE TOWN ; SONNY LANDRETH
- Levee Town
- This River
- The U.S.S. Zydecoldsmobile
- Love And Glory
- Broken Hearted Road
- Spider-Gris
- Godchild
- Turning With The Century
- Z. Rider
- Soul Salvation
- Angeline
- Deep South
SUGAR HILL SUG-CD-3925僕がサニー・ランドレスを聴くようになったのは、インターネットで「SONNYまん」というホームページに出会ったからだ。それまでは「スライドの達人」として、何曲か聴いた程度であった。このページに紹介された何枚かの CD や VIDEO を見、ネヴィル・ブラザーズがライヴで取り上げていた名曲「コンゴ・スクエア」のオリジネイターということを知るにつれ、ぐんぐんこのルイジアナのアーティストに対する関心は高まっていった。そこに届いたのがこの新作、僕にとっては今世紀の最後を飾るすばらしい作品だ。やはりただ者ではなかった。
曲は決してキャッチーなメロディを持っているわけではない。しかしじわっとしみてくる。これはサニーの郷愁と深い信仰心を秘めた歌にあるように思う。幸いなことに歌詞がついており、英語の苦手な僕でもある程度歌の世界を理解することができた。典型的なダンスナンバーである(3)などはシンプルであるが、その他の歌にはルイジアナに対する並々ならぬ愛情を感じる。タイトル曲の(1)からラストの(12)まで、ジャケットのくぐもった色とバックの沼地、ブックレットに挿入されたセピア色の写真まで、トータルなテーマとしてそれは貫かれている。
曲はビリー・ギボンズを彷彿とさせるハードエッジなスライドが響くインスト(9)がまずタイトでかっこいい。しかし同じようなギター・サウンドを持つシャッフル(1)では、裏でアコースティック・ギターやラブボード、それにジョン・ハイアットのコーラスがサウンドを和らげ、タイトなリズムを持つ(2)やいかしたインスト(6)でも、タッピングやハーモニクスを駆使しながら、時にまるでフィドルのようなサウンドで、ルイジアナの伝統を感じさせる。(8)はストレートなミディアム・ロックであるが、コーラス、メロディライン、ギターサウンドが一体となるとどこか田舎のダンス曲に感じられるから不思議だ。ダンサブルなザディコ(3)ではギターとアコーディオンが一体となって思わず体が揺れてくる。
一方フォーク調の(4)ではメロトロン風のシンセとフィドル、それにアコーディオンが哀愁を誘うし、ワルツのリズムを持つ(7)はどことなくアイリッシュ・トラッドのような響きを感じる。(10)はいかにもルイジアナ・ポップといった三連のバラードで、ボニー・レイットのコーラスがムードを盛り上げる。この曲やブラスの入る(11)で聴かれるスライドには、どことなくロ−ウェル・ジョージに通じるムードを感じる。
リゾネイタの弾き語りから始まるブルージーな(5)は、ボトムの効いた演奏で、後半のディープなスライドと合わせ、アルバムの中のアクセントとなっている。そしてこれもブラスが挿入されたラストナンバー(12)、「サウス・オヴ・I-10」に通じるいかにもサニーらしいメロディで「深南部」を歌い上げる。
アメリカの良質なロック・ミュージックが往々にしてそうであるように、このアルバムは高速道路を走るカー・オーディオで鳴らすのが爽快で良い。しかしそこで歌われた世界は決して薄っぺらなラヴソングなどではなく、地に足のついた、サニー・ランドレスというひとりの男の生きざまを感じさせるものである。じっくり噛みしめたいものだ。
HOME ・ INDEX ・ BLUES ・ SOUL/FUNK ・ NEW ORLEANS


